

小売、製造、医療…
DXの先にある未来と「成功の3条件」
DXの先にある未来と「成功の3条件」
昨今、さまざまな文脈でDXが語られているものの、成功事例は決して多くない。その背景にはどのような要因があり、成功確率を上げるためには何が必要なのか。そして新規事業と既存事業のDX、各業界のプレイヤーがDXについて考えるとき、どういった視点を備える必要があるのか。
DX専門書の著者であり、小売流通・製造・エネルギー・通信など幅広い産業でDXを支援してきたDXTコンサルティング株式会社の代表取締役 兼安 暁 様に話を伺った。
(聞き手は、KDDIソリューション事業本部 ソリューション事業企画本部 マーケティング部 マネージャー 湶 (あわら) 大輔)
- ※ 記事内の会社名、部署名、役職名は取材当時のものです。
危機感も共有しなければDXは進まない
湶 DXがなかなか進展しない企業では、「DXの定義」について社内で共通認識を持てていないケースが散見されます。
兼安さんはご著書の中でさまざまな業界のDXについて触れられていますが、こうした背景をどう捉えられていますか。

代表取締役
兼安 暁 様
兼安様 DXというと「デジタル」に目がいきがちですが、「トランスフォーメーション (変革)」のほうが重要です。
これは映画『トランスフォーマー』でロボットがクルマに変身したりするように、全く異なる形に変身することを意味します。
では、「ビジネスをトランスフォームする」とはどういうことか。それはビジネスモデル、すなわち商売のやり方を変えるということです。誰に・何を・どのような形で提供するのか、それによってお金をどのようにいただくのか。この中のいずれか一つでも変えないと、ビジネスモデルを変えたことはなりません。それをデジタルで具現化することがDX本来の意味です。
そして、そこで求められるのが戦略的思考です。生活が豊かになり、誰もが満たされた状態にある今、簡単にモノが売れなくなっています。だからこそ、顧客が求めている価値を見直し、それを提供する仕組み=ビジネスモデルを再構築していく必要があるのです。ユーザーエクスペリエンス (UX) を向上させるような商品サービスの提供が求められることにも、こうした背景が関係しています。
常にエクスポネンシャルテクノロジーをウォッチしているか
湶 DXについて考える時、新規事業創出と既存事業変革では異なる視点が求められると思います。
まず、新規事業創出をミッションとする企業の担当者がその成功確率を上げるためには、どのようなアプローチが必要でしょうか。
兼安様 テクノロジーの活用が重要な鍵となりますが、ここで言うテクノロジーとは、ITではありません。ITを含む「エクスポネンシャル (指数関数的) なテクノロジー」です。
あらゆるテクノロジーがコンピューターを活用することによって、指数曲線を描くようなスピードで進化していくものを意味します。こうした技術の活用を考えないといけないでしょう。

ソリューション事業本部 ソリューション事業企画本部
マーケティング部 マネージャー
湶 大輔
例えば、3Dプリンターを持ってきて、それをAI、あるいはIoTなど、いろいろな要素技術と組み合わせると何ができるかという話です。今までできなかったことができるかもしれない。あるいは、顧客が課題だと思っていたことがあっさり片付いてしまうかもしれません。指数関数的なスピード故、どんどん先読みしていかないと、仮に新しいビジネスを作ったとしても、出来上がった頃にはマーケットが存在しないことも考えられます。
エクスポネンシャルテクノロジーの動向を常にウォッチすること。その上で、違う技術を掛け合わせた次の未来を役員の間でディスカッションしていかなければなりません。「そのマーケットで主要なポジションを取るために、今から何をしないといけない」といった視点で考える必要があるでしょう。

湶 新規事業の成功確率を高める一方で、「そもそも成功確率は低いのだから数を打つ」という考え方もありますが、それについてはいかがですか。
兼安様 「下手な鉄砲も数打ちゃ当たる」の考えは大切ですね。例えば、10億円の投資資金があるのであれば、5,000万円の予算で20件のプロジェクトを走らせるのです。失敗する前提で取り組む覚悟も必要です。また、大企業は新規事業創出プロジェクトを進めるだけではなく、スタートアップに投資することも一つの方法です。
湶 我々もCVC (コーポレート・ベンチャー・キャピタル) を通じて、スタートアップに多数投資しています。彼らと接して痛感するのは、新規事業創出に対する気持ちや信念が非常に強く、プロセスにおいての視点やスピード感に明確な違いがあり、新たな気づきや発見があります。
兼安様 大事なことは、明確な目標を設定した上で達成しているかどうかを見ることです。達成できずに資金がショートして、次の資金調達ラウンドで投資家を説得しきれなければ解散する、といった覚悟も必要だと思います。
既存事業のDXには、競合を自社内に作る発想を
湶 もう1つのDX、既存事業の改善が効率化にとどまらないために、経営者やDX推進リーダーには、どのような視点が求められますか。
兼安様 既存事業の多くは今の「キャッシュカウ (金のなる木)」なので、力を緩めることはできません。既存事業の一部を活用して、新たな可能性を追求することも同様に重要です。
具体的な手法としては、既存事業やサービスにデジタルテクノロジーを適用したらどうなるのかを探ること。要は競合を自社内に作るのです。完成度は100%でなく、30%程度のクオリティでいい。ちょっと使い勝手がよくて、しかもリーズナブルなものが理想でしょう。当然、既存事業から利用者がスイッチすることも想定されますが、他社に取られるよりも自社内に残るからよいと考え、カニバリゼーション (共食い) は大いに歓迎すべきです。
小売、製造、医療…DXは業界の垣根すら破壊する
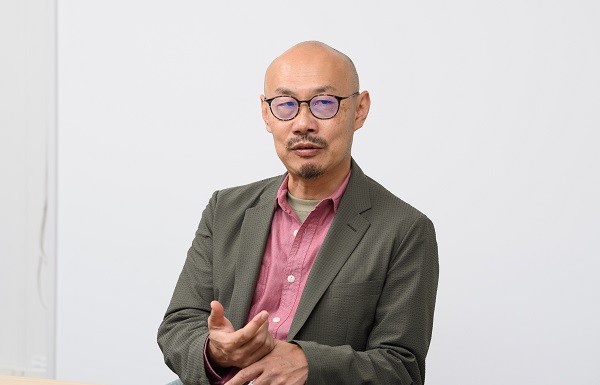
湶 続いて、業界別にいくつかDXの成功事例をご紹介いただけますか。
兼安様 小売流通の領域では、中国の大手ITグループの決済サービスがあげられます。元々はB to BのEコマースのために開発されたものですが、その成功を足掛かりに、小売店の決済業務をDXしました。現金の取り扱い業務をなくし、経理担当者が朝夕に銀行へ足を運ぶ手間も無くしたわけです。金額が合わなかった時に現金を数え直す必要もありません。こうした背景から開発された技術が「QRコード決済」です。この会社では手数料を0.6%と低く抑えたので、急速に普及していきました。
製造業では、3Dプリンターによる製品開発があります。3Dプリンターを使って、マイクロファクトリーが実現すれば、中間在庫は不要になるでしょう。また、3Dプリンターとデジタルデータがあれば、海外に工場を移しても品質は落ちません。将来的に世界の工場は、太陽光発電のコストが安価で、消費人口の多い赤道直下のアフリカに移っていくと私は考えています。
医療分野では将来的に、ウェアラブルデバイスを使って、汗の成分から血液成分を読み取る時代が来るだろうと言われています。ウェアラブルウォッチが24時間365日、さらに100万分の1秒のデータを取得していて、食事をしたり薬を飲んだりすると、それが血液にどう影響するかが見えるわけです。医者がそれを見て、「この人の薬の処方は一日一回では不十分なので2回にしよう」とか、あるいは「この食べ物は太るので、控えるように指導する」といったことも可能になるでしょう。
「究極的に何をしたいのか」というビジョンはあるか
湶 兼安さんはこれまでさまざまな業種の企業のDX支援に携わってこられたと思いますが、そのご経験を踏まえ、DXの成功とは何か、そこで求められる条件について教えてください。
兼安様 DXの成功は、次のキャッシュカウを生み出すことです。デジタルには、「プロセス自動化・無人化」「コピーし放題」「距離を超える」「時間を超える」「質量がなくなる」「誰もが所持可能」「コストを抑えられる」「大量のデータを高速処理」「すべての経験を集約して学習」という9つの特性があります。これらのいくつかを組み合わせて、新しいビジネスモデルを確立していけばいいと思います。
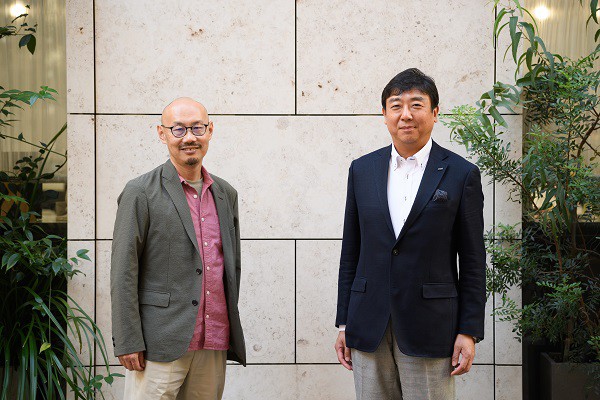
そこで求められる3つの条件ですが、1つ目は「世界観」です。
何を実現したいのか、誰にどんな価値を提供したいのか、刻々と変化する環境の中においてですから、究極的に「何をしたいのか」というビジョンが必要です。
2つ目は、そのビジョンを実現する手段を考えるために「常識的な考え方をはずすこと」。
つまり、思考の枠組みを取り払うことです。自由な発想や思考ができる人と、普段から会話のキャッチボールをしてトレーニングしていく必要があるでしょう。
そして3つ目が、「身軽になること」です。
100%を目指して石橋をたたいていたら、急な洪水でおぼれてしまうかもしれません。失敗を恐れずに、とにかくやってみることです。DXをミッションとするリーダーは、こうした点を意識することが重要だと思います。
湶 DX推進リーダーや企業組織には、これまでとは異なるマインドセットや思考が必要になるわけですね。
本日はありがとうございました。


