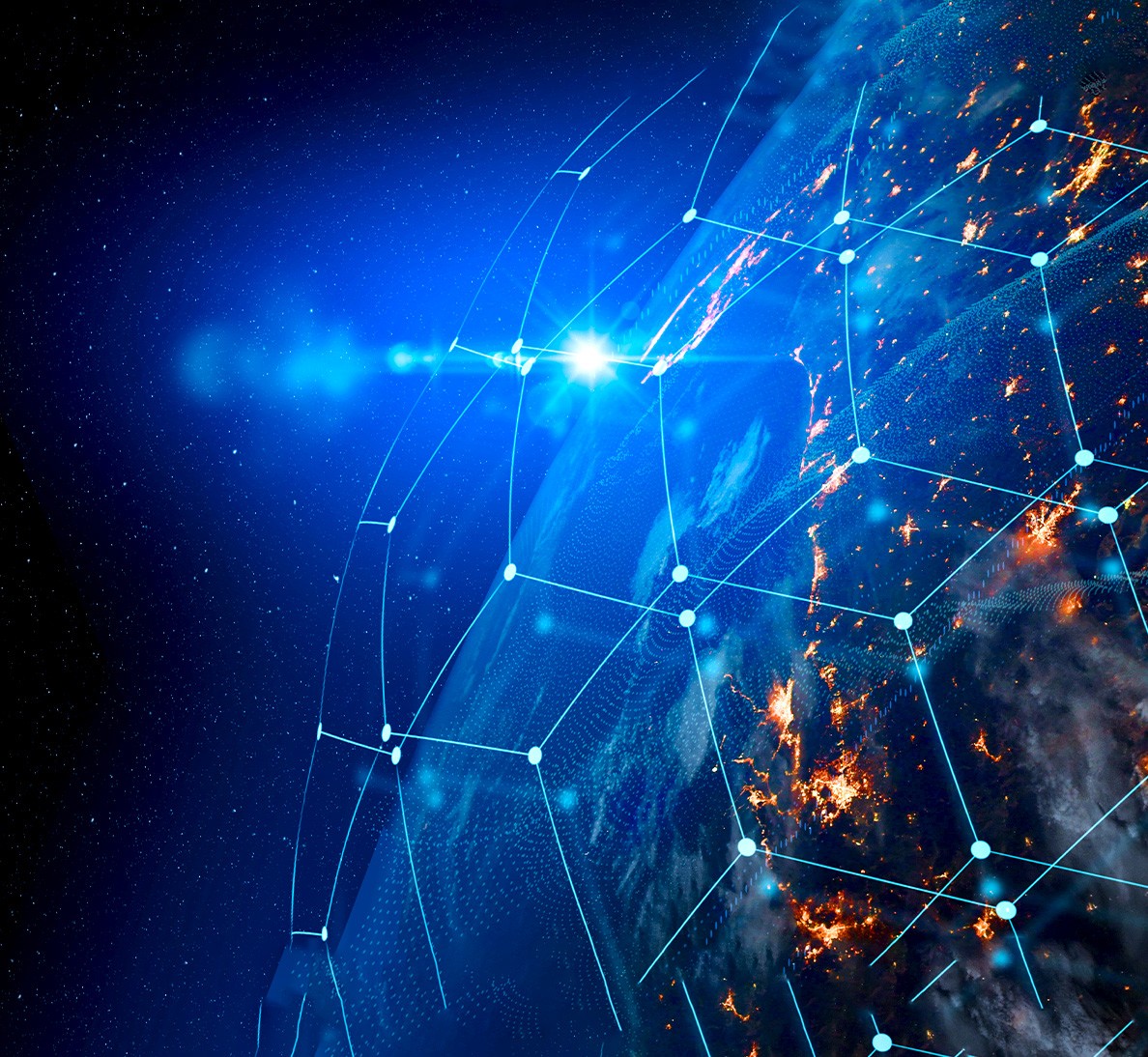例) 非常用グッズの準備、家庭内の安全対策、避難経路の確認。

災害対策とは?
減災の定義や防災との違い、取り組みと事例をご紹介
災害対策には、「防災」と「減災」という2つの視点が存在し、それぞれの役割を理解した上で適切な対応が求められます。本記事では、減災の定義や、防災と減災の違いを解説するとともに、企業における具体的な取り組みや事例を紹介します。
※ 記事制作時の情報です。
1.災害対策の重要性・必要性
災害対策とは、地震・台風・洪水などの自然災害や、建物・機械の設計ミスによる倒壊といった人為的災害に備え、被害を最小限に抑えるための計画や行動のことです。災害発生の予防や準備、災害時の救助活動、災害後の復旧・復興作業が該当します。
災害対策は、自分や家族、友人の命や財産を守るとともに、社会機能の迅速な回復や経済活動の早期再開を目指すものです。特に、大規模災害では、適切な対策がなければ被害が拡大し、二次災害を引き起こすおそれがあります。
2.「自助」「共助」「公助」の視点
災害対策には、個人や家庭が主体となる「自助」と、地域や社会が連携して取り組む「共助」、そして国や自治体が主導する「公助」があります。相互に補完し合う関係にあり、それぞれが機能することで効果的な災害対策が可能となります。
災害への備えは、「自助」「共助」「公助」それぞれの役割を理解し、適切に実践することが大切です。
3.個人でできる災害対策

一人ひとりが災害に備えることで、被害を抑えられます。個人でできる災害対策として、以下の3つを紹介します。
- ハザードマップの確認と避難計画の策定
- 非常用グッズの準備と管理
- 家族間の安否確認手段の確保
3-1. ハザードマップの確認と避難計画の策定
まず、自分の住む地域や職場周辺のハザードマップによるリスクを把握しましょう。特に危険区域や避難場所を事前に確認しておくことで、いざというときの的確な判断と迅速な避難につながる可能性が高まります。
3-2. 非常用グッズの準備と管理
次に、自宅や職場、車内に非常用グッズを備えましょう。食料や水、モバイルバッテリー、ラジオ、懐中電灯、救急用品が該当します。災害時でも使えるように、定期的に消費期限や電池残量を確認しておくことが大切です。

3-3. 家族間の安否確認手段の確保
最後に、家族間での安否確認手段を確保しましょう。災害時には「災害用伝言ダイヤル (171) 」や「災害用伝言板」を活用します。
4.「防災」と「減災」の違い
「防災」とは、自然災害が発生する前に対策を講じ、被害を最小限に抑えるための活動を指します。一方、「減災」は災害発生を前提として、その影響をできる限り抑える考え方・行動指針です。
例えば、地震における建物の耐震補強や防波堤の整備、土砂崩れへの対策は「防災」に該当し、避難訓練の実施、ハザードマップの作成、非常用グッズの準備は「減災」です。
4-1. 企業における減災とは
企業における減災とは、一般的な防災対策とは異なり、事業継続の観点から被害を最小限に抑えるための取り組みを指します。
一般的な減災は、個人や地域社会が自然災害による人的・物的被害を減らすことを目的とし、避難計画や耐震補強などの対策が含まれます。
一方、企業の減災は、従業員の安全確保に加え、災害発生後も事業を継続し、迅速に復旧することを重視します。企業は、物理的な被害の軽減だけでなく、サプライチェーンの維持やデータ保護、事業継続計画 (BCP) の策定が不可欠です。
このように、単なる防災の領域を超え、経営資源を守り、取引先や顧客への影響を最小限にすることが、企業の減災の特徴といえます。
5.企業における減災の必要性
ここでは、企業における減災の必要性について詳しく解説します。
5-1. 事業への影響を軽減する

減災対策は、災害発生時にも迅速に事業復旧・継続することを目指す取り組みです。甚大な被害は、企業経営に深刻な影響をおよぼすおそれがあります。
そのため、従業員の雇用維持、取引先企業の保護、地域社会の早期復旧に向けた備えが重要です。
5-2. 従業員の安全を守る
東日本大震災以降、自然災害を完全に防ぐことは難しいという認識が広がり、被害を最小限に抑える「減災」の考え方が政府の重要課題として位置づけられました。(注1)
内閣府の防災情報サイト「みんなで減災」(注2) では「企業は、従業員や顧客の安全を第一に防災活動に取り組まなければなりません」と明示されており、企業にも積極的な対応が求められています。災害対策において、従業員と顧客の安全確保を何よりも優先すべきです。
5-3. 社会的責任を果たす
減災対策は、企業の社会的責任 (CSR) (注3) の履行において重要な取り組みです。適切な対策による事業の継続性確保と雇用維持は、地域社会への貢献につながります。
- 注1) 参考:内閣府「第3章 政府として今後更なる取組が求められる災害対策― (1) 災害対策の理念の明確化」(外部サイトへ遷移します)
- 注2) 出典:内閣府「防災」(外部サイトへ遷移します)
- 注3)「Corporate Social Responsibility」の略で、企業が社会や環境に配慮しながら事業を行うこと。
6.企業が行うべき5つの減災対策
企業が取り組むべき減災対策を紹介します。
6-1. 災害対応ガイドラインの整備
災害発生時の円滑な行動に向け、防災マニュアルを作成することが不可欠です。災害発生時の役割分担、情報収集・避難方法、連絡体制といった対応策をまとめ、社内で共有することで、緊急時の混乱を抑えられます。
現在は、対策に役立つツールやアプリケーションが数多く存在するため、使用するツールのアップデートや、最新情報の反映など、マニュアルの定期的な見直しが必要です。

6-2. 非常用物資の備蓄
災害発生時に備えるには、水や食料だけでなく、乾電池や非常用発電機などの電源確保用品、携帯ラジオ、救急用品、消毒液やマスクなどの衛生用品といった多様な物資の備蓄が欠かせません。さらに、定期的に消費期限や品質を確認し、必要に応じて補充・交換を行うことで、緊急時に備えることができます。
6-3. オフィス家具の安全対策の実施
地震発生時の什器の転倒・移動・落下などによる被害を防ぐため、配置を見直し、什器を固定することも不可欠です。また、避難経路や出入り口、什器の上には物を置かないなど、安全確保を徹底することが望ましいでしょう。窓ガラスへの飛散防止フィルムの貼り付けや、避難誘導灯の見やすい位置への設置も効果的です。
6-4. 拠点ごとの災害危険性評価

企業の拠点ごとに異なる災害リスクの把握も重要です。海沿いや山間部、市街地など、拠点の地理的条件によって、津波、土砂災害、浸水といったリスクの内容や度合いは異なります。ハザードマップを活用し、各拠点のリスクに基づいた減災対策を講じましょう。
6-5. 災害時用の連絡体制の構築
災害時には迅速な安否確認と情報共有が不可欠で、緊急連絡網を事前に準備しておくことが大切です。電話、メール、SNS、安否確認システムといった複数の連絡手段を組み合わせ、連絡の優先順位や手順を決めておきましょう。
また、災害用伝言ダイヤル (171) は主に家族や友人向けのサービスであり、企業では安否確認システムの導入を検討すべきです。
7.減災対策の取り組み事例
7-1. 災害対策訓練に「Starlink Business」を活用
東日本大震災の教訓を基に、東京都では大規模災害時に発生する帰宅困難者への対策を強化しており、訓練も繰り返し実施しています。
その一環として、2023年8月4日に「令和5年度東京都・足立区合同帰宅困難者対策訓練」が行われ、新たな防災DXの取り組みとして衛星通信サービス「Starlink Business」を非常時の通信インフラとして活用する実証が行われました。
実証の流れは、以下のとおりです。
- 北千住駅周辺で滞留していた帰宅困難者が、一時滞在施設である東京電機大学へ誘導されました。
- 施設の受付には「Starlink Business」を用いるためのWi-Fi情報 (SSIDおよび暗号化キー) が掲示され、帰宅困難者は各自のスマートフォンでその情報を入力し、通信手段を確保しました。
- 入館受付に必要な氏名などの個人情報はLINEを介して登録しました。
登録した情報は「帰宅困難者対策オペレーションシステム」と連動する仕組みです。
7-2. KDDIの迅速な通信復旧体制の強化
KDDIは、災害時の迅速な通信の復旧を目指し、車載型基地局や仮設電源の導入を進めるとともに、地上での通信が困難な場合には衛星通信を活用するなど、複数のアプローチで安定した通信を確保しています。2024年1月に発生した能登半島地震では、KDDIは災害発生からわずか3分後に災害対策本部を設置し、現場の通信復旧作業に着手しました。被災地の状況をリアルタイムで把握し、復旧に必要なリソースの迅速かつ適切な配備を通じて、早期の通信回復を実現しています。
7-3. 「Starlink」の提供により避難所での通信環境を改善
KDDIは、SpaceX様の日本法人「Starlink Japan」様と提携し、石川県能登半島の避難所などに衛星ブロードバンドサービス「Starlink」を無償で提供しました。軽量で携帯性に優れた小型アンテナを採用しているため、短時間でWi-Fi環境を整備できることが特長です。低軌道衛星の活用により、被災地においても高速かつ低遅延のインターネット接続を実現しています。
また、通信インフラの復旧で、被災者はニュースや災害情報に加え、SNSや動画配信サービスを通じた情報収集も可能になりました。さらに、スマートフォンゲームや動画配信サービスの娯楽も楽しめるようになり、多くの避難者から喜びの声が寄せられています。
8.まとめ
災害対策は、企業の事業継続性を支えるだけでなく、従業員や地域社会に対する責任を果たす重要な取り組みです。
災害に備えたガイドラインの整備、備蓄品の準備、通信手段の確保といった、具体的な対策を着実に進め、将来のリスク軽減を図ります。技術の進化や新しい取り組み事例を活用しながら、災害に強い組織づくりを目指しましょう。
災害対策をご検討中の方はKDDIへ
KDDIは、車載型基地局や仮設電源、衛星通信技術を駆使し、被災地における迅速な通信復旧を実現しています。また、防災DXの推進にも注力し、最新技術を活用した効率的な災害対策を展開中です。さらに、「Starlink」などの衛星通信を用いた新しい通信ソリューションや、BCP (事業継続計画) 支援サービスにより、企業や自治体が災害に備える体制を構築することができます。
災害対策を強化したい、もしくは新たな対策を検討したいとお考えの方は、ぜひKDDIにご相談ください。