
フルリモート× Iターン / Uターンで、マネージャーとして働く選択肢
※ 記事内の社名、部署名、役職は取材当時のものです。
テレワーク主体の働き方へ、
社員の1割強が地方在住のKDDIウェブコミュニケーションズ
—早くから働き方改革に取り組んできたと伺っていますが、現在の働き方や人財採用について教えてください。
神森様 弊社では以前から、フレックスタイム、分割勤務、時短勤務など、社員自らがライフスタイルにあわせた働き方を選べるよう、さまざまな制度を整えてきました。また、事業継続の観点から、自宅でもオフィスと同様に仕事ができるよう、テレワーク制度も導入していました。そして、東京都から外出自粛要請のあった2020年3月末から「全社員在宅勤務」をスタートしました。
これに伴い、長期の在宅勤務への対応として、自宅環境整備のための補助金や夏の電気代を一時的に支給したほか、通勤費支給を停止し在宅勤務手当の支給に切り替えるなど、制度の見直しも進めてきました。
社内コミュニケーション活性化のため、社員紹介や社内ニュースを知らせる動画「ラジ広報」も配信。健康経営への取り組みや、社内勉強会補助制度をオンラインにも適用するなど、働き方の変化に合わせて福利厚生の拡充にも努めています。
採用活動も説明会から面接まですべてオンラインにシフトし、地方採用も積極的に進め、Iターン / Uターンを含めた地方在住社員は全体の11%に上っています。
テレワークシフトをきっかけに宮古島オフィスへIターン
—神森様が東京から宮古島に拠点を移したのはどんなきっかけでしたか。部下もいらっしゃるマネジメントの立場で、業務上のハードルや不安はなかったでしょうか。

広報室 室長
神森 勉 様
神森様 2016年に開設した宮古島オフィスの現地採用社員が退職することになりました。そこで社長が「宮古島で働きたい人がいれば、上司と相談のうえ希望を出してください」と全社員に投げかけたのがきっかけです。
私は沖縄が大好きでコロナ禍前は何度も足を運んでいたので、チャンスだと思って手を挙げたんです。2020年3月末からテレワークが始まり「意外とテレワークで仕事ができる」と実感していたことも後押ししました。
広報室は社長直属部門なので、社長と部門メンバーとも話し「特に業務遂行には問題ないだろう」ということで移住に踏み切りました。ですので、社内的なハードルはなかったです。
正直、業務や部門メンバーをマネジメントしていく不安も少しありましたが、それまでもオンラインでずっとコミュニケーションを取っていましたし、とにかくやってみようと。
—実際に環境が変わって、仕事への向き合い方や業務上の変化はありましたか?
神森様 業務時間自体は東京で働いていた頃と全く変わっていません。広報室メンバー専用にZoomの会議室をいつでも入れるように発行しており、メンバーには「声をかけてもらえればいつでも入ります」と伝えています。その都度ミーティングをセットするよりも気軽に声をかけやすいですよね。実際、何かあると連絡が入るのですぐにコミュニケーションが取れ、仕事面では以前とも違和感がない状態です。
変化があるとすれば、当社の働き方の制度をフル活用するようになったことです。例えば、分割勤務制度を利用した業務間の中抜けです。ちょっと天気がいいと、メンバーに「中抜けします」と伝えて、勤怠システムへ退勤打刻します。海に出て写真を撮ったり景色を眺めたりして、またオフィスに戻って夜まで仕事をする、そんなスタイルですね。日常と仕事がシームレスに緩くつながっている感じです。

テレワークに不安なし、地元福岡で転職したVPoEエンジニア
—小山様が地方採用でKDDIウェブコミュニケーションズに入社した経緯を教えてください。
小山様 もともと福岡出身なんです。東京で13年働いていて、35歳までに地元に戻るかどうか考えていたのですが、前職の縁でUターンすることに決めました。
Uターンを決めた理由は2つあります。福岡は現在スタートアップやテクノロジー企業に注力しており、私自身もその分野で地元に貢献したいと考えたこと、そして1人でどの程度できるのか力試ししたいという思いがありました。VPoE (Vice President of Engineering) として仕事をしていたとき、KDDIウェブコミュニケーションズから声を掛けられ入社しました。
—最初から部下がいるマネジメントの立場で入社して、フルリモートに不安はなかったのでしょうか。
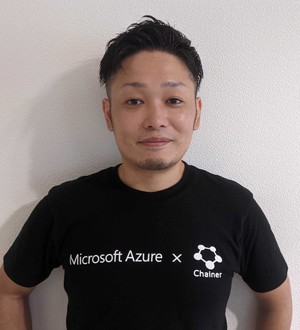
技術本部 アプリケーション開発部 ゼネラルマネージャー
小山 哲洋 様
小山様 エンジニア畑なので、もともとリモートワーク自体は経験していたんです。抵抗はほとんどなく、むしろもっと早くこの働き方になっていてほしかったと思っています。
入社して最初にやったのはマネージャーとしての仕事でした。チーム開発が多いので、まずメンバー全員と面談をして、その人がどういうことを求めているのか、どういうタイプの人なのかを把握し、仕事の進め方や特徴を掴んでいきました。
実はチームメンバーと直接会ったのは、出張で東京に行った時の一度だけです。チームメンバーは9人で、福岡、沖縄、東京の3拠点で仕事をしている状態です。フルリモートだからといって、新しい環境に馴染むことや業務上の苦労も特に感じませんでした。普通に出勤していてもリモートワーク下でも、何かわからないことがあったら周囲に尋ねるのは普通のことですし、そこで聞いた内容と自分の経験を照らし合わせて物事を考えたり、会話しながら社風に馴染んでいったり、社内ドキュメントを見たりしながら学んでいく、その本質は変わらないと思います。
リモート環境でチームをマネジメントする工夫
—フルリモートでどのようにチームをマネジメントしているのか、その工夫をそれぞれ教えてください。
小山様 チームメンバーとは2週間に1回、1on1を実施しています。時間は15分と短いのですが、普段ちゃんとリフレッシュできているのか、どんな時間の使い方をしているのか、こまめに聞くようにしてアラートを見逃さないようにしています。
不安や不平不満ももちろん聞きます。そこで意見が出てくるのであれば自己分析がある程度できているのでいいのですが、あまり出てこないメンバーは逆に気に掛けるようにしています。
ミーティングはつい長くなりがちなので、メリハリが重要だと思っています。
メンバーから業務の相談を受ける場合も基本的には15分で区切ります。まだ煮詰まっていないなと思ったらそこで打ち切り、できるだけメンバーが自分の業務に集中して考える時間を確保できるよう意識しています。担当プロジェクトに関係なく、純粋に技術的な内容についてシェアしたり質問したりする雑談の機会も設けていますね。普段接することのないメンバーと接点をもつきっかけにもなりますし、チーム全体としてもスキル向上につながっていくと思います。
私自身、メンバーとリアルに会うのは月3回もあれば十分だと感じますし、フルリモートの今の働き方には満足しています。
今後、海外エンジニアも含めたリモートワークが可能になれば、仕事のアウトプットもさらに面白いものになっていくのでないでしょうか。
神森様 私のチームは少数精鋭部隊で、移住前は直接会う機会がたくさんあったので、正直それほど工夫はしていないんです。
それまで普通にコミュニケーションを取っていたので、各メンバーの特性もだいたい把握しているつもりですし、テレワークになってからはむしろパフォーマンスを落とさないよう、働き方はメンバーに一任しています。
そういう意味では、部下に恵まれていると思っています。
強いて挙げれば、やはり何かあった時にすぐに相談に乗れる環境でいることでしょう。手が空いていなくても、とりあえず「少し待っていて」とすぐに反応する。リモートでお互いの状況が見えにくいからこそ、そういうことを心がけています。
私もいまの働き方に満足していますし、これからも続けていきたいと思っています。当社は社員1人ひとりが「どう働くか」を考える会社なので、私がここ宮古島でどう働くのか、多様な働き方の1つとしてその姿を見せていければいいなと考えています。
そして、こういう働き方ができるということを1人でも多くの方に知っていただき、「一緒に働きたい」と思ってくれる方がいればとても嬉しいです。
柔軟で自由な働き方の実現へ、KDDIがサポート
神森様と小山様の働き方で示されているように、各人が自分の人生や生活のプランに合わせ、場所や時間にとらわれず柔軟に働くことができる時代です。今年も、テレワークやハイブリッドワークが当たり前の世代が新社会人として歩み始めています。
企業にとって、ビジネス環境や状況に合わせた働き方の変化は、今後も求め続けられるでしょう。
KDDIは、変化する働き方を通信とテクノロジーで引き続き支援していきます。



















