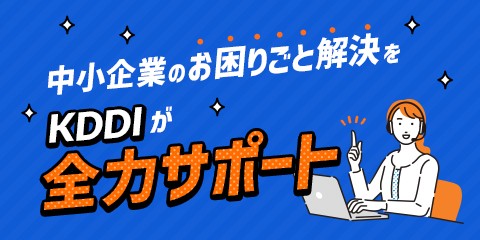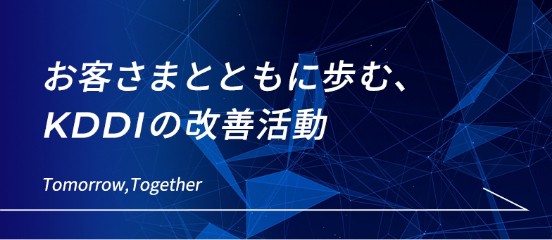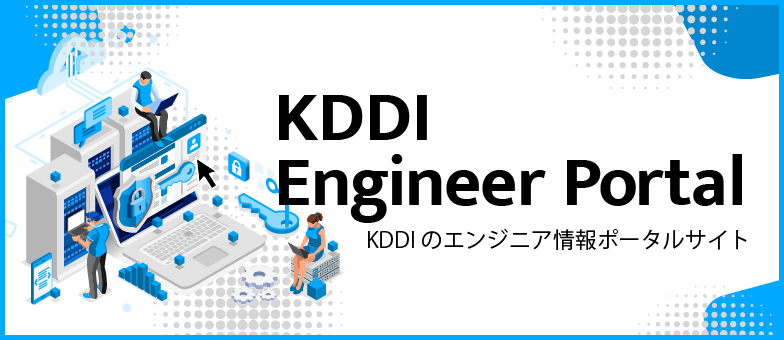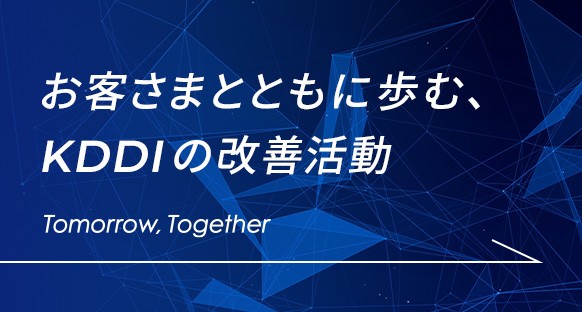-
「つなぐチカラ」をよりシンカさせ、あらゆる社会課題に立ち向かう。
-
多数の次世代型低軌道衛星により高速・低遅延通信を提供します。
-
KDDIは『つなぐチカラ』でビジネス、ライフスタイル、社会をアップデートします。
-
場所にとらわれずつながるソリューションを、デバイスからセキュリティまで支援します。
-
KDDIは、グローバルビジネスの成長をお客さまと共に実現します。
-
CO2排出量の可視化から削減まで、一貫してカーボンニュートラル実現を支援します。
-
中小規模の事業者向けに特化したスマートフォンのご利用方法のご案内です。
-
中小規模事業者のやりたいことや変えたいことを、モバイルとクラウドの技術を用いてサポートします。

見えてきた「新しい働き方」成功のコツ
業務を円滑に進めるにはどうすればいいか、コミュニケーションロスを防ぐ最適な方法は何か、といった次々に現れるテレワーク特有の課題に企業はもちろん、従業員自身も、この1年対処を続けて、少しずつ新しい様式が社会に根付いてきました。
2021年2月26日にJTB、シスコシステムズ、PHONE APPLIを迎えてオンライン開催したセミナー「スマートワークの実態を本音で語る~全面テレワークから2年目の働き方とコミュニケーション~」より、1年経って見えてきたテレワークの現実と、目指すべき理想像を実現するヒントについてご紹介します。
※ 記事内の社名、部署名、役職は取材当時のものです。
ワーケーションで、生産性や仕事の満足度が向上
2020年、激変した社会生活の1つに、働き方の変化があります。オフィスへの通勤や人との接触を極力控え、インターネットを介して業務を進めるようになりました。こうしたスタイルを一般的にテレワークと呼び、より生産性やコミュニケーション向上に注力した新しいスタイルをスマートワークと呼ぶこともあります。
2021年2月26日のオンラインセミナー「スマートワークの実態を本音で語る~全面テレワークから2年目の働き方とコミュニケーション~」では、そんなスマートワーク実現に向け、見えてきた課題と解決策について、識者に講演・ディスカッションいただきました。
――第一部「ニューノーマル時代の新しい働き方〜ワーケーションの効果と可能性〜」――
ワーケーションの実現に必要な‘‘3つのこと‘‘とは?
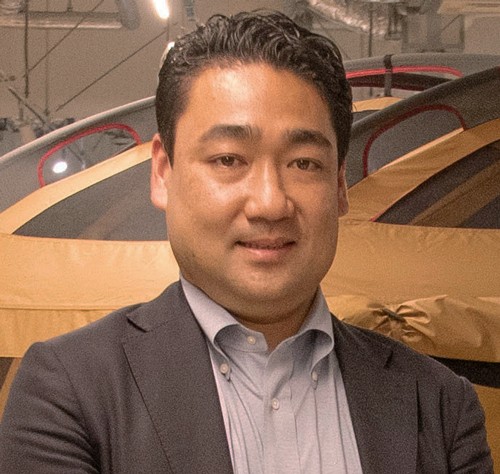
新宿第一事業部 営業課長
原 周太郎 様
JTBは、多様な働き方の選択肢の1つとして、リゾート地など普段の職場と異なる場所で働く「ワーケーション」の効果を確認すべく、研究機関や企業と組み、実証実験を行っています。
株式会社JTB 新宿第一事業部 営業課長 原 周太郎 様 (原様) によると、ワーケーションとは、「休暇中に働く」という意味ではなく、「休暇前後やその最中でも働ける環境を整備して、自分のスタイルに合わせて仕事を取り入れられる」ことを指すといいます。
「いつもと違う場所で働くことで、何が違うのか」という疑問もあるでしょうが、実は、オフィスや在宅勤務以外の環境で仕事をすることは、仕事の生産性に貢献することが分かっています。実際に、JTBが関係各社と共同で実施したワーケーションの効果・効用に関する実証実験では、ワーケーションが生産性や心身の健康に与えるポジティブな効果がいくつも見られました。
原様は「従業員側は、生産性向上やストレスの軽減を実感できますし、企業側も、従業員のエンゲージメント向上や、生産性アップによる業務効率の向上といったメリットが期待できます」と、その効果を説明します。
一方で、ワーケーションのデメリットには、社内理解が得づらい、オン・オフの切り替えが難しい、コミュニケーションの取りづらいといったといったことが挙げられます。
これらを解決するには、“3つのこと”を行い、自ら非日常感を高めることで、「メリットを最大化できます」と原様はいいます。
その「3つのこと」とは何か? 当日の講演をぜひ末尾のリンクから動画で確認してみてください。
――第二部「スマートワークの実践に必要なコミュニケーション」――
テレワークのメリットとデメリット
JTB原様のほか、シスコシステムズ 執行役員 人事本部長 宮川 愛 様 (宮川様)、PHONE APPLI 取締役副社長 中川 紘司 様 (中川様)がディスカッションを行いました。モデレーターを務めたのは、KDDI サービス企画開発本部 サービス戦略室 室長 山田 高です。
テーマは「リモートワークのメリットと課題」「社員がイキイキと働く環境作り」「今後実現したい働き方」の3つ。
まず最初のテーマ、「リモートワークのメリットと課題」については、
「離れた場所にいる人との会議・コミュニケーションが多くなった」(原様)、「地方のサテライトオフィスとの情報格差がなくなった」(中川様)、「新しい物事への取り組みが進んだ」( 宮川様)と、多くのメリットを感じている反面、やはり「同じチーム内でのコミュニケーションが希薄になった」、「一人一人が意図を持って積極的にコミュニケーションする必要がある」といった課題が顕在化したそうです。また、「組織としての統一感がなくなった」(中川様)という意見も。こうした課題に対し、各社はどのように対応しているのでしょうか。
「意図的に雑談する機会や場を設けている」(宮川様)や、「1on1を改善し、上司は部下の仕事やメンタル、モチベーションの状況を事前に共有して仕事に当たるようにした」(中川様)
という施策のほか、「あえて『管理』をせず、チームの自主性に任せる雰囲気作りを進めた」(原様)などの対策で成果を上げているそうです。
なお、PHONE APPLIでは社員ごとに家族環境や住環境を基にアセスメントして、定期的に仕事の悩みや現状の課題をヒアリング、都度積極的に対策
を講じるようにしたとのこと。
「自宅内で働く環境があまり整備されていない」という社員には、「テレワーク用の折り畳み式簡易ブースを送りました」(中川様)といいます。
大切
なことは、見えた課題にとにかく対策を講じてみること。
「違ったら、別の手段にシフトすればいいのです」と中川様は説明します。

取締役副社長
中川 紘司 様
大切なのは「信頼関係」の構築、具体的な対策を動画で紹介!

執行役員 人事本部長
宮川 愛 様
社員がイキイキと働く環境作りについては、
「監視ではなく、上司が部下の仕事のしやすさを意識すること、仕事そのものをマネジメント・評価するプロセスを見せること」(宮川様)、「離れていても、信頼関係を構築すること」(中川様)がキーポイントといえます。
これを受け、原様は「多様な働き方、多様な価値観を組織が認め、選択肢として用意することが、採用や生産性向上につながっていくと思います」と述べ、「自分らしい働き方やスタイルを実現できる文化や体制が企業にあること、これこそが今後はより重要になってくるはず」との見解を示しました。
講演では、具体的にその仕組みをITでどのように実装していったのか、各社の取り組みが紹介されているほか、本記事では紹介しきれなかった知見・エピソードが惜しみなく披露されています。
テレワークやスマートワークに興味がある方、本格的に働き方改革に取り組みたい企業の方は、ぜひ下記より講演をご覧ください。
スマートワークの実態を本音で語る
~全面テレワークから2年目の働き方とコミュニケーション~
下記フォームより、お申し込みください。