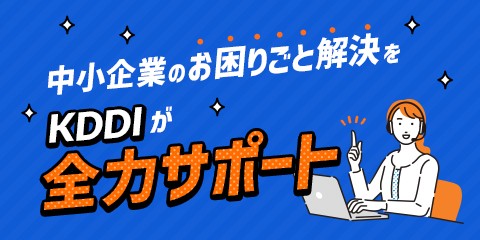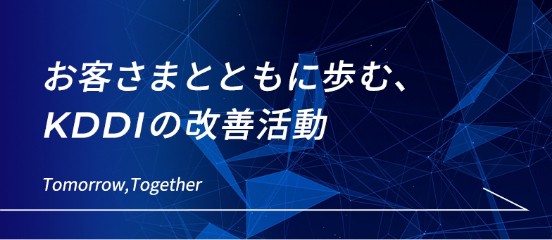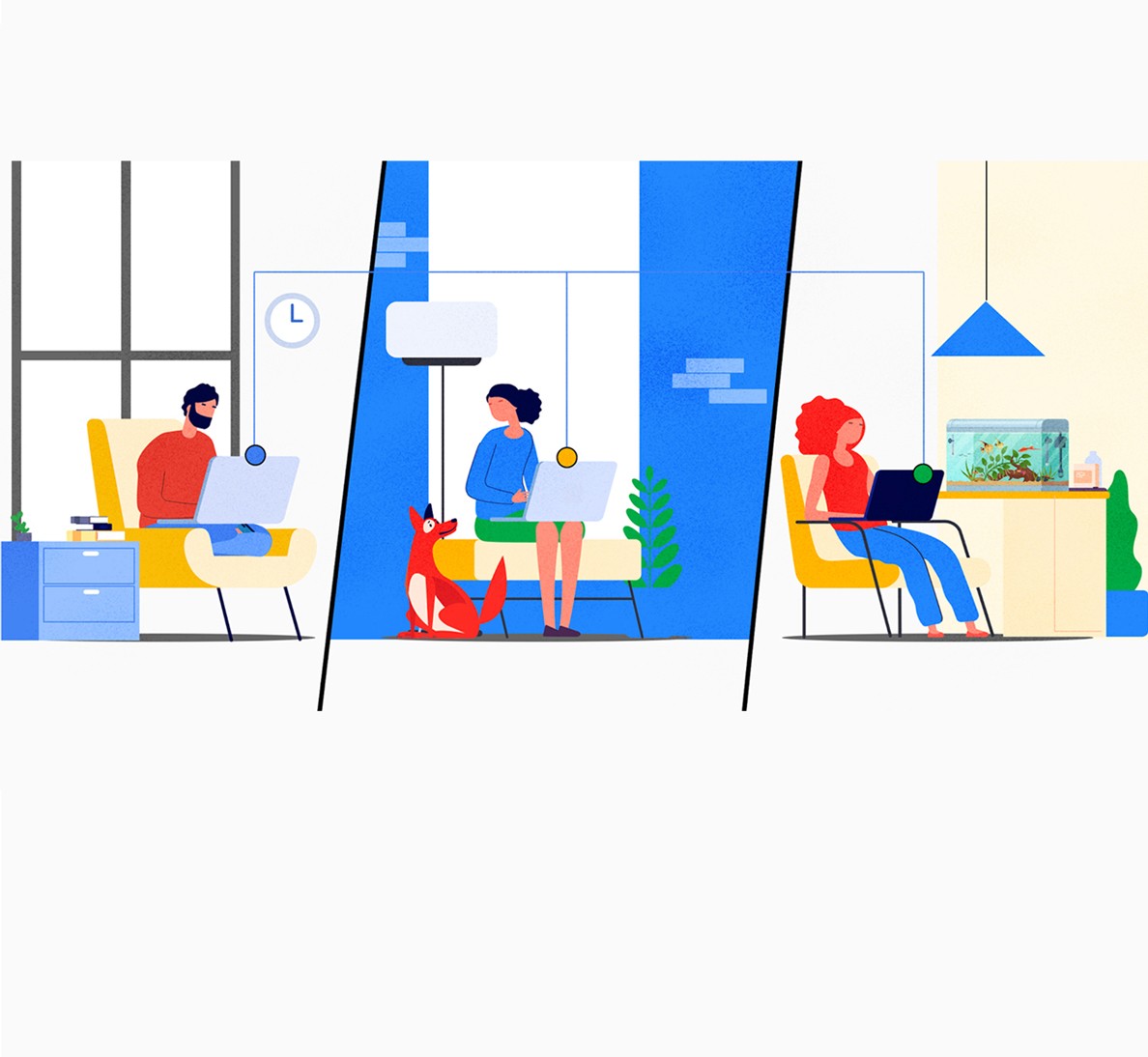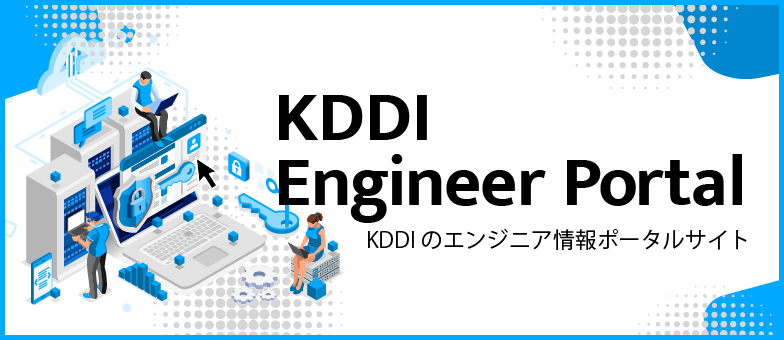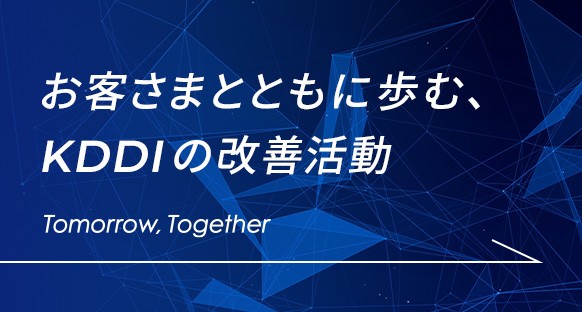-
「つなぐチカラ」をよりシンカさせ、あらゆる社会課題に立ち向かう。
-
多数の次世代型低軌道衛星により高速・低遅延通信を提供します。
-
KDDIは『つなぐチカラ』でビジネス、ライフスタイル、社会をアップデートします。
-
場所にとらわれずつながるソリューションを、デバイスからセキュリティまで支援します。
-
KDDIは、グローバルビジネスの成長をお客さまと共に実現します。
-
CO2排出量の可視化から削減まで、一貫してカーボンニュートラル実現を支援します。
-
中小規模の事業者向けに特化したスマートフォンのご利用方法のご案内です。
-
中小規模事業者のやりたいことや変えたいことを、モバイルとクラウドの技術を用いてサポートします。

感染症の蔓延で目の当たりにした、テレワークの必要性と導入時のポイント
1. 感染症の拡大において、なぜテレワークが必要だったのか

内閣府男女共同参画局によると、テレワークとは『ICTを活用し、場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方のこと』を指します。
個人の生活に合わせた働き方であると同時に、2020年に国内で感染者が多発している『新型コロナウィルス感染症』のような、危険性を示されている感染の拡大を防止する役割もテレワークにはあります。
特に、都会であればオフィスに通うために混雑する通勤電車やバスなどを乗り継ぐ人は多いもの。人との接触が増えると感染リスクが高まるとされ、危険を防ぐためには、テレワークによる在宅勤務を推奨するのが妥当とも考えられます。実際、新型コロナウィルス感染症対策本部からは、テレワークや時差出勤の推進の呼びかけがなされました (注)。
また、テレワークの推進は、レピュテーションリスクの回避にもつながります。感染症の拡大が危惧されている中での出社義務の保持は、従業員を危険な目に合わせるものだと判断され、大幅に企業の信頼を落とすこともあるからです。
企業側はテレワークの推進を行うことで、従業員やその家族だけではなく、周囲からの評価を守ることにもつながるかもしれません。
2. テレワークは、従業員の働きがいや採用などにも効果を発揮する
テレワークが企業にもたらすメリットは数多くあります。顕著なのは、優秀な人材の採用につながることではないでしょうか。今の時代、場所にとらわれずに働きたい、子育てや介護と両立しながら働きたいと望む人は多く存在します。
オフィスへの出社義務があることで、そういった希望を持つ人々の採用機会を逃す可能性もあります。自社に必要な優秀な人材を採用できない、離職率が上がるということにもなりかねません。
またテレワークによって柔軟な働き方が可能になると、すでに働いている従業員にもメリットがあります。来客対応や雑談などによって阻害されていた業務を集中して行えるようになり、業務効率が向上することも考えられます。
さらに通勤時間が削減されるため、今まで通勤に当てていた時間を別の趣味やリフレッシュなどに当ててワーク・ライフ・バランスを保つことにもつながります。
3. テレワークを整備する上で意識したい3軸
厚生労働省は、テレワークの整備にあたり、6つの分類とぞれぞれの留意点や内容をまとめています。
| 分類 | 留意点 | 内容 |
|---|---|---|
| セキュリティ | セキュリティに関する漠然とした不安 | どのようなセキュリティ対策を行えばいいかわからない、またはセキュリティ対策を行ったが、情報流出などが発生するのではないかという不安 |
| 情報漏えいのリスクの軽減 | 内部の機密情報などが外部に漏れてしまうリスクの軽減 | |
| 第三者からののぞき見、端末の紛失、盗難の防止 | 関係者以外に情報が見られること、機密情報の入ったパソコンの紛失や盗難の防止 | |
| 人事・労務管理 | 個々のテレワーク実施者の労務管理の難しさ | テレワーク実施者の適切な勤怠や在席、 業務管理の実施 |
| コミュニケーション | テレワーク実施者と通常勤務者の間の円滑なコミュニケーション | テレワーク中の円滑な情報伝達・交換の促進や、テレワーク中の疎外感軽減 |
| 作業効率 | 通常オフィス勤務時と変わらない作業効率の確保 | 特定のアプリケーションやグラフィックなどを多用する場合における、 通常と同様の作業効率や生産性の確保 |
| 電子化の遅れ | 資料の電子化、 管理ツール導入の遅れ | オフィス以外で作業するための資料の電子化や、 テレワークを実施するための管理ツールの導入の遅れ |
| 予算制約 | ICT投資予算の制約 | 企業規模が小さい場合に、 ICT投資予算の制約があること |
これを基に整理すると、テレワークの導入にあたって意識するべきなのは3軸となります。
『セキュリティの見直し』『制度の整備』『ツールの整備』です。順番に見ていきましょう。
他にも、ファイルや資料の共有ツール、オンライン上で会議を行うためのツールなど、社外からでも日常業務が滞りなく行える、「Microsoft 365 with KDDI」Google Workspace など『グループウェア』を整えなくてはなりません。現在の業務のうち、何がツールを必要とするものなのか洗い出しながら、必要なツールを厳選します。
また、グループウェアを導入してテレワークを行う際、一番齟齬が発生しやすいのがコミュニケーションです。言葉足らずだったり、情報が正しく伝達できていなかったりと、慣れないことが初期は多いはず。
そのため、チャットツールで何気ない雑談をできる環境を作ったり、オンライン会議で顔が見える時間を作ったりと、ツールを駆使しながら快適な環境を生み出すことが必要です。
実践していく中で要望や課題が見えてくるので、全てを完璧に整えてからテレワークを導入するのではなく、随時整える心持ちでいるのがよいでしょう。
次回のコラムでは『中小企業が考えるべき従業員や関係者の安全確保』について、解説します。