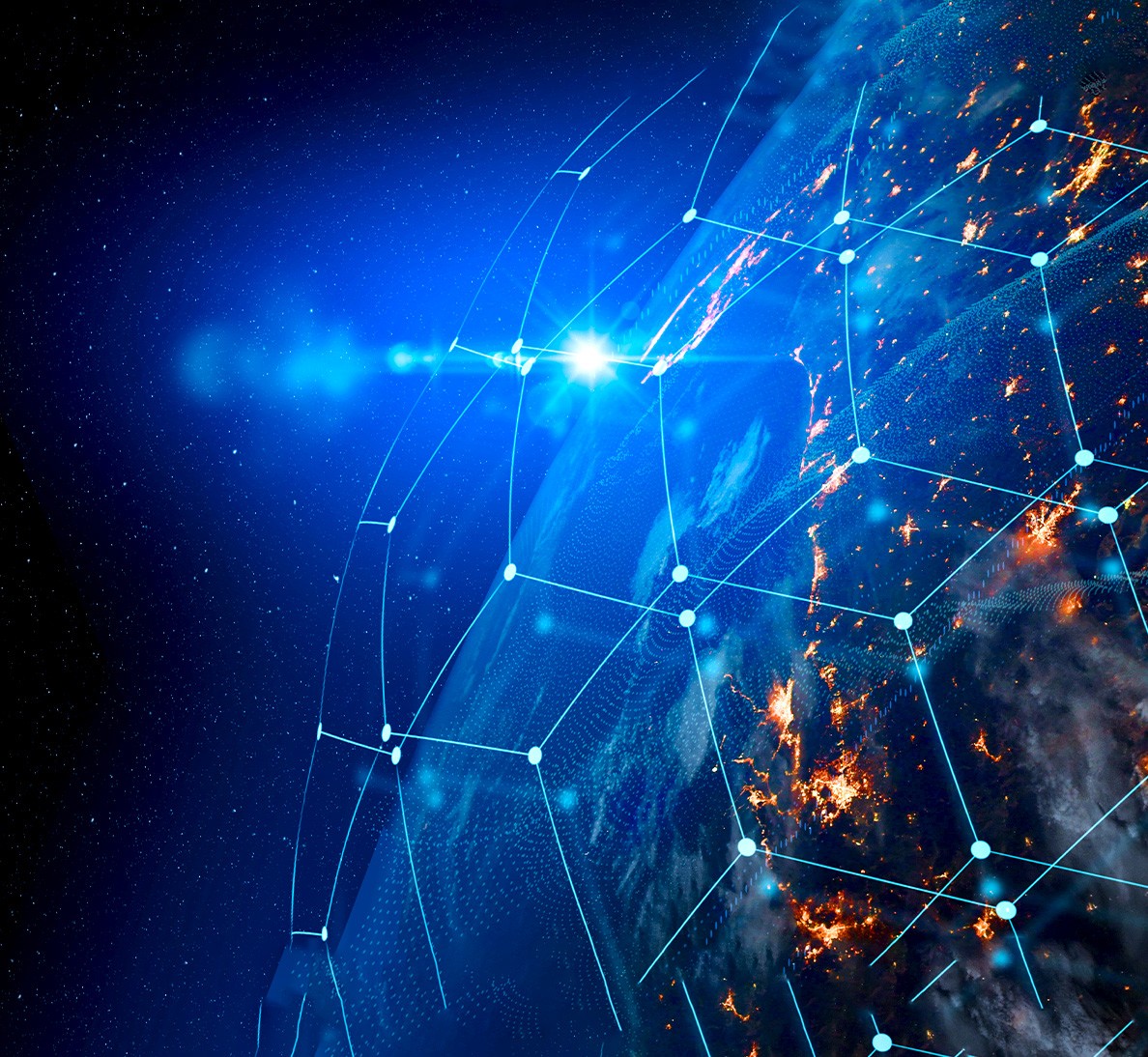DX推進とは何か簡単に解説|企業の取組事例も紹介
本記事では、DX推進の定義やIT化との違い、注目される理由、導入メリットを解説するとともに、実際に成果を上げた成功事例を紹介します。自社での取り組みを考えるうえでの具体的な指針を得られる内容です。
※ 記事制作時の情報です。
1.DX推進とは何か
DX推進とは、単なるIT導入や業務効率化にとどまらず、企業の経営や事業そのものをデジタル技術で変革し、新たな価値を生み出す取り組みです。企業を取り巻く環境は、人口減少、労働力不足、国際競争の激化といった外部要因により急速に変化しており、従来型の業務改善だけでは対応できなくなっています。
こうした背景を受け、経済産業省が2024年9月に改訂した「デジタルガバナンス・コード3.0」では、副題を「DX経営による企業価値向上」とし、経営層に対してDXを経営課題の中心に据えるよう強く促しました。
特に注目すべきは「DX経営に求められる3つの視点・5つの柱」で、以下のように整理されています。
| 視点 | 柱の内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 戦略性 | [1] 経営ビジョンとDX戦略 | DXは経営ビジョン実現に直結する中長期投資 |
| 実行力 | [2] 組織・人材戦略 [3] ITシステムとサイバーセキュリティ |
人材育成と安全な基盤の整備が不可欠 |
| 成果と監督 | [4] 成果指標 (KPI) [5] ガバナンスと監督 |
成果を数値で測定し、継続的に改善する体制が必要 |
上記は、従来の「システム整備のための指針」から一歩進み、人的資本経営やサイバーセキュリティへの対応も含めて、DXを経営戦略そのものと結びつける内容となっています。
このようにDX推進は、単なるIT導入や効率化の延長線ではなく、変化の激しい市場環境に柔軟に適応し、投資家や消費者の期待に応えるための中長期的な経営戦略です。企業が持続的に成長し、将来にわたって企業価値を高めるために、DX推進は欠かせない取り組みといえます。
1-1. DXの定義

経済産業省はDXを以下のように定義しています。
「データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」
この定義は、DXが「効率化」にとどまらず「経営や事業のあり方そのものを変革し、競争優位を確立する」ことを示しています。
具体的には、以下のような変革を伴います。
- 新しいビジネスモデルの構築
- 組織文化や人材育成の変革
- 競争優位の確立を目的とした投資
これらを同時に進めることで初めて、DXは企業の長期的成長を支える戦略となります。クラウドやIoTの導入自体はIT化に過ぎませんが、そこから需要予測や新サービスの創出に発展させることこそがDXの本質です。
1-2. DX推進とIT化の違い
DX推進とIT化の最大の違いは「取り組みの目的」です。
IT化は、既存の業務プロセスを前提としながら、その効率を高めるためにデジタル技術を活用します。例えば、紙の請求書を電子化して経費精算システムに一本化することで、入力作業や書類保管にかかる時間とコストを削減できます。
このように、IT化の主な目的は既存業務の効率化やコスト削減です。紙の請求書を電子化して経費精算システムに一本化するといった施策が挙げられます。これらは、入力作業や書類保管にかかる時間とコストを削減する目的があります。
一方、DX推進は効率化にとどまらず、企業の経営や事業そのものを再設計する取り組みです。例えば、メーカーが製品にIoTセンサーを組み込み、稼働状況を遠隔監視して故障予兆を分析し、「モノを売る」だけでなく保守サービスを組み合わせたビジネスモデルへと拡大する取り組みが挙げられます。
つまり、DX推進は新たな価値を生み出し、企業を成長させるための戦略といえます。
2.DX推進が注目されている背景
DX推進が注目される背景には、社会や産業の構造変化があります。主な要因は以下の3点です。
- AIなどテクノロジーの進化
- 2025年の崖問題
- 労働力の減少
2-1. AIなどテクノロジーの進化
AIやIoT、クラウド、5Gといったテクノロジーの進化は、DX推進を後押しする最大の要因です。膨大なデータをリアルタイムで収集・分析し、より精緻な判断や自動化が可能となりました。
例えば、需要予測や設備保全、顧客行動分析など、従来は人手と時間を要した業務が自動化されたことで、新しいビジネスモデルの構築が現実的となっています。こうした技術革新が企業に変革の必要性を突き付けており、DXに注目が集まっています。
2-2. 2025年の崖問題
「2025年の崖」とは、DXの取り組みが進まなければ企業の国際競争力が大幅に低下するリスクのことです。老朽化システムを維持し続けると、セキュリティの脆弱性が増大し、古い技術に精通した人材が減少することで、保守運用の人材不足が深刻化します。
その結果、2025年以降は年間で最大12兆円の経済損失が生じる注2) と試算されています。こうした背景から、システム刷新とDX推進は企業にとって喫緊の課題です。
2025年の崖については以下の記事をご覧ください。
2-3. 労働力の減少
日本では少子高齢化の影響で労働人口が年々減少しており、多くの企業で人材不足が深刻化しています。特に中小企業では採用難が続き、限られた人員で生産性を維持する仕組みづくりが急務です。
この課題に対し、例えば製造業では、IoTを活用して生産ラインを自律制御し、従来は複数人が担当していた監視・操作業務を最小限の人員で行えるようにします。そのうえで、空いた人材を生産データの分析へ再配置する例があります。
こうした取り組みが、一人当たりの生産性の向上や、企業全体の競争力強化につながるでしょう。
3.DX推進に取り組むメリット
DXを推進することで、企業はさまざまな恩恵を得られます。主なメリットは以下の3点です。
- 人手不足解消のうち手となる
- 生産性が劇的に向上する
- 最新のテクノロジーの使用によって競争力を高められる

3-1. 人手不足解消のうち手となる
DXは、人手不足を補うための有効な手段です。少子高齢化による労働人口の減少や採用難によって、多くの企業が必要な人材を十分に確保できない状況に直面しています。こうした課題に対してDXを活用することで、限られた人材で業務を回せるようになり、持続的な成長につながります。
例えば、RPA (ロボティック・プロセス・オートメーション) を導入すれば、請求書処理やデータ入力といった定型業務の自動化が可能です。これにより、従業員は単純作業から解放され、付加価値の高い業務に注力できるでしょう。実際に導入企業では、経理や人事部門の業務量が大幅に削減され、残業時間の短縮や人材不足の解消につながった事例も報告されています。
3-2. 生産性が劇的に向上する
DXを推進する大きな目的の一つが、生産性の向上です。AIやIoTを活用すれば、従来は勘や経験に頼っていた判断をデータに基づいて行えるようになり、業務の精度とスピードが飛躍的に向上します。
例えば製造業では、IoTセンサーで設備の稼働状況を可視化し、AIで異常を検知することで、突発的な故障や生産停止を未然に防げます。結果として稼働率が高まり、無駄なコストを削減しながら効率的な運営を実現可能です。
また、サービス業においても、顧客データをAIで分析することで需要予測や最適な人員配置が可能となり、顧客満足度を維持しつつ少人数で高い成果を上げられる体制を築けます。
3-3. 最新のテクノロジーの使用によって競争力を高められる
DX推進は、新しいテクノロジーを積極的に取り入れることで企業の競争力を大きく高める取り組みです。AIやクラウド、5G、ビッグデータ解析などを活用すれば、従来は把握しきれなかった市場動向や顧客ニーズをリアルタイムで捉え、迅速に事業戦略へ反映できます。
例えば小売業では、購買履歴や位置情報を分析してパーソナライズした提案を行うことで、顧客満足度を高められます。製造業では、5GとIoTを組み合わせて「つながる工場」を実現し、生産性と品質の両立が可能です。こうした取り組みは単なる効率化にとどまらず、競合との差別化や新たなビジネスモデルの創出につながり、持続的な成長を後押しします。
4.DX推進に取り組むステップとポイント

DXを成功させるには、段階的に進めることが欠かせません。具体的なステップは以下の3つです。
- 解決したい課題を明確にする
- DX推進の体制を整える
- 試行錯誤を繰り返しながら進める
4-1. 解決したい課題を明確にする
DX推進の第一歩は、技術導入ありきではなく、自社が抱える課題を洗い出すことです。顧客体験の改善か業務効率化なのか、目的が曖昧なままでは成果につながりません。経済産業省も、経営ビジョンと課題を結びつける重要性を指摘しており、課題の優先順位づけが成功の鍵となります。
4-2. DX推進の体制を整える
DX推進を成功させるには、経営層が関与する推進体制を整えることが重要です。
経営戦略と現場を結びつけ、迅速な意思決定を行うために、CDO (最高デジタル責任者) や専任部署を設けて、IT部門と現場部門をつなぐ橋渡し役を明確にします。
また、外部パートナーと連携して、セキュリティや人材育成も含めた総合的な仕組みを整えます。
4-3. 試行錯誤を繰り返しながら進める
一度に完成形を目指すのではなく、小さな取り組みを実行し、改善を重ねることがDX成功の近道です。社会や市場環境は常に変化しているため、最初から完璧な設計は困難であり、柔軟な対応が求められます。
例えば、新しい顧客向けアプリを試験導入し、利用データを分析して機能を改善するなど、アジャイル的な進め方が有効です。現場の反応を素早く取り入れ、失敗から学び施策を磨くことで、変化に強い仕組みを構築できます。
5.DX推進の成功事例
5-1.【金融】Starlink Businessで非常時の通信を確保
大規模災害時でも取引を止めないために「Starlink Business」を導入し、拠点間の通信を強化しました。平時からWeb会議やチャットで活用し、有事には即時切り替え可能な体制を整えたことで、BCPの実効性を高めています。
【課題】
社会インフラを担う取引所として、大規模災害発生時でも業務を継続する必要がありました。また、従来の衛星携帯電話は1対1の通話に限られており、天候や環境に左右されず屋内でも安定して使える通信基盤が求められていました。
【解決策と効果】
「Starlink Business」を導入することで、東京と大阪の拠点をつなぎ、大規模な災害時もスムーズなコミュニケーションを確保。高速・大容量・低遅延の通信性能により平時から活用し、緊急時にスムーズに切り替えられる体制を整えています。通話以外にWeb会議、チャット機能といった連絡手段が追加、利用可能な人数の増加にもつながりました。
関連記事: お客さま導入事例 株式会社日本取引所グループ様
5-2.【鉄道】KDDI IoTクラウド Data Marketで商圏分析を高度化
メッシュでのきめ細かな人流分析が可能な「KDDI IoTクラウド Data Market」を導入し、携帯端末の匿名位置情報を活用して人流データを精緻に可視化しました。商圏分析や出店計画の精度が高まり、地域活性化につながっています。
【課題】
事業環境の変化に即応するため需要変化を正確に把握する必要がありました。特に、コインパーキング新規開業や料金見直しの判断精度の向上が求められていました。
【解決策と効果】
「KDDI IoTクラウド Data Market~Location Analyzer~」を導入し、10mメッシュの詳細な人流データを活用し需要変化を見える化しました。曜日・時間帯別の滞在人口や属性の把握により開業判断や料金見直しを高精度に行い、売り上げアップにつなげています。
関連記事: お客さま導入事例 名古屋鉄道株式会社様
5-3.【地方自治体】KDDI IoTクラウド Standardで農業負担を軽減し復興を支援
災地の復興と地域産業の再生に向け、AI・IoTを活用した「幸満つる 野蒜農園」プロジェクトを推進しました。圃場データをクラウドで一元管理できる「KDDI IoTクラウド Standard」により、高齢者や障がい者も従事しやすい農業環境を整え、品質と収穫量の安定化、地域雇用創出につなげています。
【課題】
東日本大震災により津波被害を受けた跡地の利活用が課題となっていました。また、農業施設の運営にはスタッフの作業負担軽減と安定経営に向けた品質向上が求められていました。
【解決策と効果】
「KDDI IoTクラウド Standard」を導入し、ネットワークカメラやAI潅水・施肥システムを活用することで、圃場管理や水やりの作業を自動化しスタッフの負担を大幅に軽減しました。さらに、栽培データをクラウドに蓄積して分析することで、適切な管理が可能となり収穫量は最大2.4倍、糖度も平均0.9向上につながりました。
関連記事: お客さま導入事例 宮城県東松島市様
そのほかの事例については以下をご覧ください。
関連記事:【DX事例】DXの成功事例を紹介
6.まとめ
DX推進は単なるシステム導入ではなく、企業全体の構造や文化を変革する大きな取り組みです。AIやIoTといった先端技術の進化、2025年の崖問題、労働力の減少などの社会的背景を踏まえると、もはや待ったなしの課題といえます。
実際の成功事例が示すように、人手不足の解消や生産性の向上、新しい価値創造を可能とするDXは、中小企業にとっても競争力維持のカギとなります。
DXを実現したい方はKDDIへご相談ください
KDDIは、AI時代のビジネスプラットフォーム「WAKONX」を通じて、お客さまのDXを支援します。通信基盤からクラウド、AI・IoT、セキュリティまで一貫して提供が可能な総合力を強みとし、多様な業界でのDX推進を支援しています。
BCP対策や業務効率化、商圏分析など幅広い分野で培った知見を活かし、企業の変革を着実に後押しします。お客さまの課題解決に最適なソリューションのご提案し、DXを支援します。詳しくは以下をご覧ください。