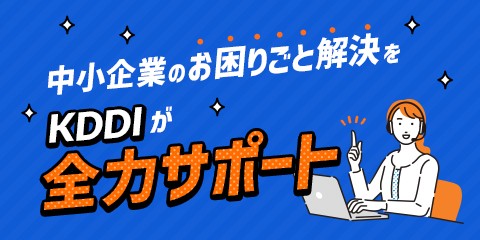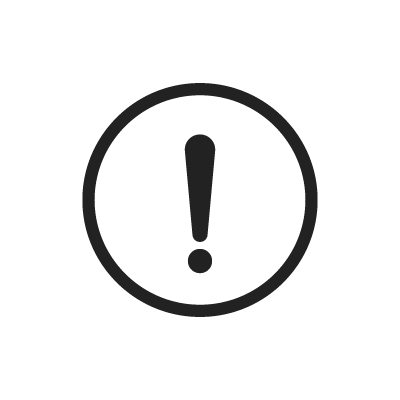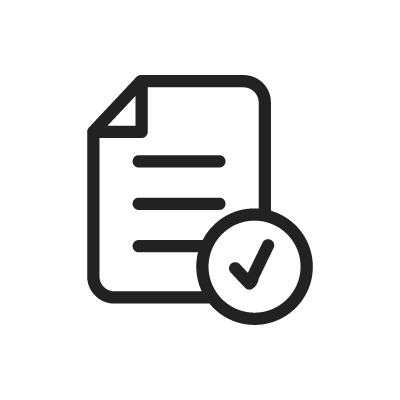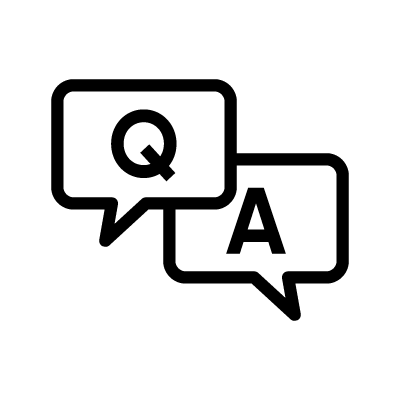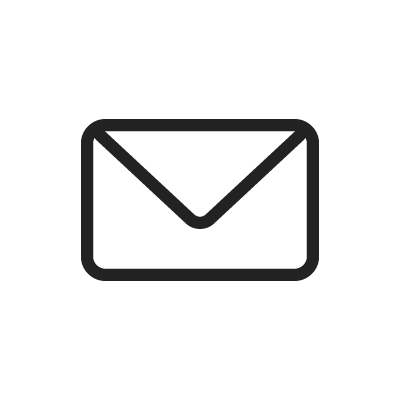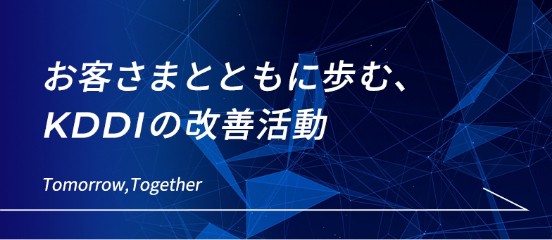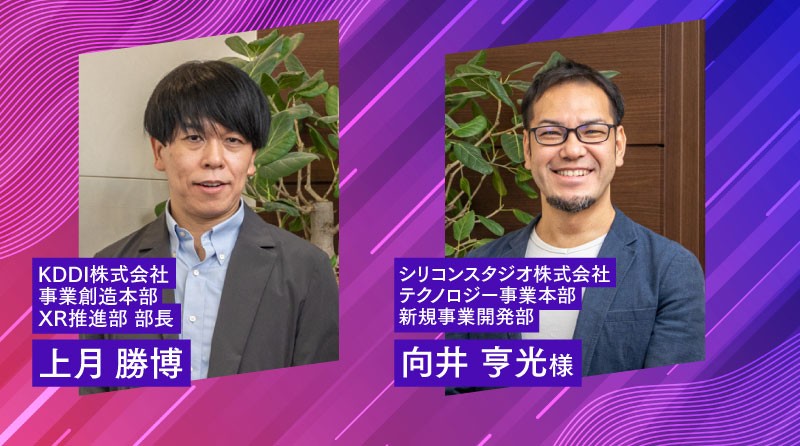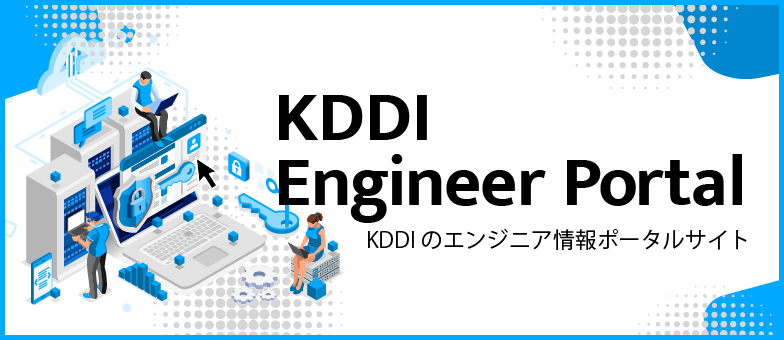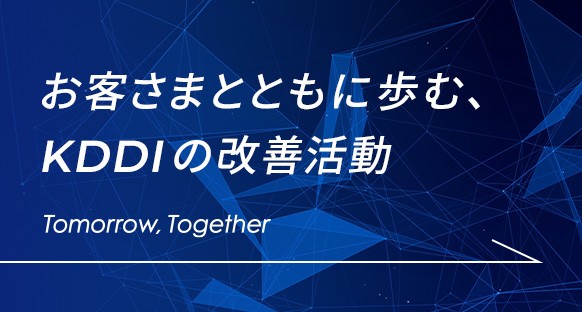-
通信と多様なケイパビリティを活用し、DXと事業基盤サービスでお客さまビジネスを支援します。
-
CO2排出量の可視化から削減まで、一貫してカーボンニュートラル実現を支援します。
-
KDDIは『つなぐチカラ』でビジネス、ライフスタイル、社会をアップデートします。
-
場所にとらわれずつながるソリューションを、デバイスからセキュリティまで支援します。
-
多数の次世代型低軌道衛星により高速・低遅延通信を提供します。
-
データセンターからネットワークまで、業務に最適なソリューションをトータルで提供します。
-
中小規模の事業者向けに特化したスマートフォンのご利用方法のご案内です。
-
中小規模事業者のやりたいことや変えたいことを、モバイルとクラウドの技術を用いてサポートします。
-
KDDIは、お客さまにご不便をおかけするような通信・回線状況が発生した場合、本ページでお知らせします。
-
お支払い方法の変更や請求書の再発行方法、その他ご請求に関する便利なサービスなどをご案内します。インボイス制度対応についてはこちらからご確認ください。
-
よくあるご質問についてお答えいたしております。お問い合わせの際には、まずこちらをご覧ください。
-
お問い合わせフォームサービスご利用中のお客さまへ、フォームでのお問い合わせをご案内します。電話でのお問い合わせ先は、各サービス別サポート情報からご確認ください。
お役立ち情報
「お役立ち情報」は、ビジネスに関わるKDDIのさまざまな情報をお届けするポータルサイトです。
KDDIの取り組みだけでなく、意外と知らないテーマに関するコラム記事や現場エンジニアが執筆するブログ記事などをご紹介!
あなたの「ちょっと困ったな」を解決するヒントをお届けします。

最新記事
セキュリティ特集
ゼロトラスト環境の構築に向け、解説記事やエンジニアブログなどで、セキュリティ対策について分かりやすくご紹介します。
グローバル特集
国内外でのIoTやセキュリティ、ネットワークインフラにお悩みの方にオススメです。
AI特集
生成AIに関するさまざまな情報をお届け。導入の方法や活用方法をお探しの方はご覧ください。
災害対策特集
ネットワークインフラの断絶を避けるため、衛星通信をはじめとした各種情報をお届けします。